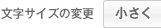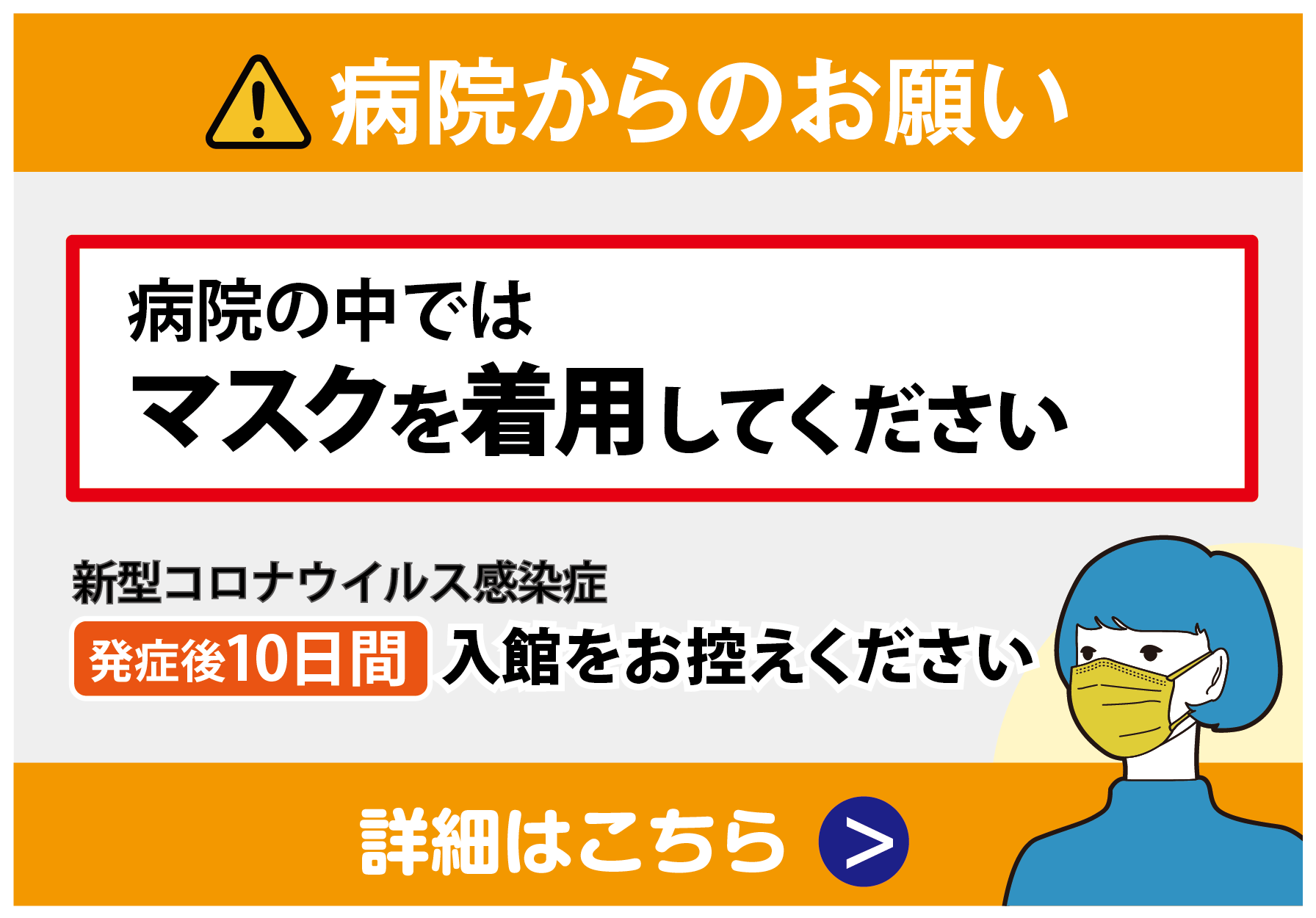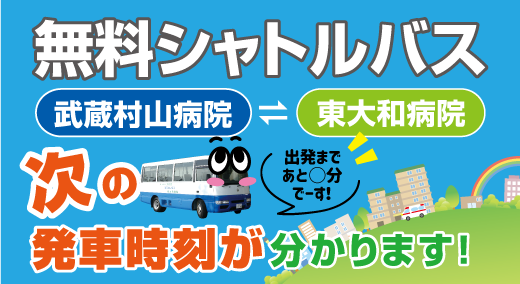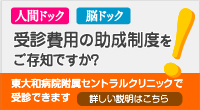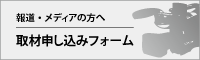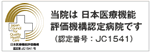院内感染対策指針
院内感染対策指針の目的
武蔵村山病院(以下、「当院」という)における院内感染防止対策の基本方針を定め、患者および全職員、訪問者を医療関連感染から防御し、安全で質の高い医療を提供することを目的にこの指針を定める。
【1】 院内感染対策に関する基本的な考え方
当院は、市民に信頼される地域医療の中核となる「市民のための病院」として、良質で安全な医療を提供することを使命とする病院である。医療機関においては感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者が同時に存在する事を先ず前提とし、その上で、医療関連感染を未然に防止するとともに、感染症が発生した際には拡大防止のため、その原因を速やかに特定して、これを制圧、終息させることが重要である。院内感染防止対策は医療を安全に行う上で優先事項であり、全職員が感染防止対策の必要性を認識し、遵守して安全で質の高い医療を提供することを目的に本指針を作成する。
【2】 院内感染対策のための委員会等の組織に関する基本的事項
(1)院内感染防止対策委員会(infection control committee ; ICC)
院内感染防止対策委員会は、院長・看護部長・事務部長・感染管理担当医師・感染管理担当看護師を含めた各関係部門の責任者または責任者に任命され、院長が認めた者を構成員として組織する感染管理における最高決定機関である。毎月1回定期的に会議を開催する。また、緊急時、必要時は臨時委員会を開催することができ、必要と認める職員の出席を求め、意見の聴取及び資料の提出を求めることができる。
【委員会の事務】
- 院内感染対策の検討・推進に関すること
- 院内感染防止の対応及び原因究明に関すること
- 院内感染等の情報収集及び分析に関すること
- 院内感染防止に関する職員の教育・研修に関すること
- その他院内感染対策に関すること
(2)ICT(infection control team ; ICT)
院内感染防止対策に関する実働組織。医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師で、ICCのメンバーの中から院長から指名を受けたメンバーにより構成される。専門性を生かし、院内感染発生状況、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止対策の実施状況などの把握を行うとともに、具体的な提案・実行・評価をする役割を担う院長直轄組織として設置する。
【ICTの業務】
- 院内感染事例の把握とその対策指導
- 院内感染防止対策の実施状況の把握とその対策の指導
- アウトブレイクの早期発見、原因分析及び対策
- 院内感染対策マニュアルの作成や見直し、及び職員の遵守状況の把握と指導
- 職員の教育及び定期的な研修の開催
- 針刺し切創、皮膚粘膜曝露事故の発生時の対策、院内感染の発生防止ならびに発生状況の把握、分析及び対策
- コンサルテーション業務
- ファシリティーマネージメント、各種ワクチン接種等
- 感染対策に関する他施設や外部委託業者との調整に関すること
- 定期的なカンファレンス、ラウンドの実施
(3)抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team;AST)
抗菌薬を使用する際、不適切な使用や長期の投与が、薬剤耐性微生物を発生あるいは蔓延させる原因となりうるため、その薬剤耐性微生物対策として抗菌薬の使用を適切に管理、支援するための実働部隊として、各職種の専門性を生かし、協力しながら組織横断的な活動を行うこと目的として設置する。ICTとの兼務を妨げず医師、薬剤師、臨床検査技師、感染管理認定看護師、その他感染対策に関連のある構成員で設置する。
【ASTの業務】
- 管理抗菌薬の使用状況のモニタリング
- 初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行う
- 適切な検体採取と培養検査の提出状況、血液培養検査実施状況、複数セット採取率のモニタリング、アンチバイオグラムの作成
- 抗菌薬使用量・使用日数及び耐性率などの定期的な評価及びフィードバック
- 抗菌薬使用マニュアルの作成及びアップデート
- 抗菌薬適正使用のための教育、啓発活動
- 連携強化加算取得の医療機関から、抗菌薬使用状況の報告、必要時抗菌薬適正使用の推進に関する相談等をうける
- 外来での抗菌薬処方状況をモニターし、推奨される抗菌薬の使用を促す
(4)感染対策リンクスタッフ委員会
部署における感染対策上の問題を把握し、解決に向けて活動することにより現場での感染管理活動を推進し、病院全体の感染対策がより徹底することを目的としてICC、ICT/ASTの下部組織として設置する。看護師、薬剤師、理学療法士、臨床工学技士、放射線技師等から委員を選出して部署内の状況報告や感染対策の周知、確実な浸透を図る。毎月1回、定期的に会議を開催し、院内を巡回し感染対策上必要な知識・技術の習得、部署職員への連絡、教育を行い、実践的で現場に密着した活動により感染対策の充実に努める。
【3】 院内感染対策のための病院職員に対する研修に関する基本方針
感染対策に関する基本的な考え方及び具体的な対策の周知徹底、及び感染対策に関する意識向上を図り、職員全員で組織的な院内感染対策に取り組むため研修を行う。
- 全職員を対象とした院内感染対策に関する研修を年2回以上実施する。これらの研修では、院内感染対策に必要な教育、実習などを行う
- 全職員を対象とした院内感染対策に関する研修では、同一内容での複数回の開催やオンデマンド配信を活用するなど参加を支援する。また、不参加者に対してはフォローアップ体制を整備する。また、病院職員外の委託会社職員についても、院内で安全に業務を果たすために必要な研修を開催する
- 新規採用者、中途採用者に対しても必要な教育を行う
- このほか、職種別、部署別の研修、コンサルテーション、現場介入などによる教育を必要に応じ、随時実施する
- 院外の感染防止を目的とした各種学会、研修会への参加など、情報や新しい知見や訓練を受ける機会を推奨、支援する
- 研修の実施内容(開催日時、出席者数、研修項目等)または、外部研修参加実績(受講日時、研修項目等)を記録・保存する
【4】 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的、組織的に収集して、的確な感染対策を実施できるよう各種サーベイランスを実施する。
- MRSAなどの耐性菌のサーベイランス
- 伝播力が強く院内感染対策上問題となる各種感染症のサーベイランス
- 外来・入院病棟における新型コロナウイルスやインフルエンザ迅速検査者数及び陽性者数、発熱等患者数、職員における感染症罹患による就業制限状況のサーベイランス
- カテーテル関連血流感染・尿道留置カテーテル関連尿路感染・手術部位感染などの対象限定サーベイランスを可能な範囲で実施する
- 厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)に参加し、院内の状況を報告するとともに、参加施設の還元情報を活用する
【5】 院内感染発生時の対応に関する基本方針
- 各種サーベイランスをもとに院内感染のアウトブレイクあるいは、異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含め迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う
- 療養病棟においては中心静脈カテーテルに係る院内感染防止対策のための指針を作成するとともに中心静脈カテーテルに係る院内感染の発生状況を把握する
- 検査科と連携し、検体からの検出菌の薬剤感受性などの分析を行い、疫学情報を日常的にICT及び臨床側にフィードバックする
- アウトブレイクあるいは異常発生時には、その状況及び患者への対応等を病院長に報告する。院内感染防止対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために職員への周知徹底を図る。状況に応じ保健所、東京都福祉保険局に報告し対応について指示を確認する
- 感染症法上の報告を義務付けられている感染症が特定された場合は、速やかに保健所に報告を行う
【6】 患者さまに対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- この指針は院内LANを通じて全職員が閲覧できる。また、本院ホームページにおいて患者又は家族が閲覧できるようにする
- 疾病の説明とともに、感染症の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める
【7】 当院における院内感染対策推進のために必要な基本方針
- 院内感染対策の推進のため「院内感染防止対策マニュアル」を作成し、全職員に周知徹底を図るとともに、定期的な見直しや改訂を行う
- 職員は自らが感染源とならないよう、定期健康診断を1年に1回以上受診し、健康管理に留意するとともに、病院が実施するB型肝炎やインフルエンザをはじめとするウイルス性疾患ワクチンの予防接種を積極的に受ける。また必要と認めたときは、臨時に健康診断、予防接種その他の措置をとる
- 院内感染(二次感染・クラスター等)を発生させないことを職員全員が共通認識して取り組み、発生時においても一般診療の機能を守りながら適切な感染症診療を機動的に行っていく
- 地域全体での感染防止活動と質の向上に取り組む
- 保健所及び地域の医師会と連携し、連携する医療機関と年4回以上のカンファレンスを実施する。また、このうち1回は新興感染症の発生等を想定した訓練を実施する
- 感染対策向上加算1を取得する施設と相互評価活動を実施する
- 専従の感染管理担当看護師により、年4回以上、連携する医療機関を訪問し院内感染対策に関する助言を行う
- 連携する医療機関から感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を受け、必要時に院内感染対策に関する助言を行う
- 連携する高齢者施設等と感染症発生時の協力体制を構築し、求めに応じて適切な助言等を行う
- 新型インフルエンザ等の新興感染症が国内で発生・まん延した際には、医療措置協定に基づいて感染症患者対応のための病床確保、発熱外来の設置、人材派遣等を行う。そのために、平時から感染防止技術についての職員教育、受け入れ体制・導線・ゾーニングの確認、防護具等医療資材の確保を行い、また、有事の際の情報収集、意思決定、他施設との連携、院内感染症患者対応部署と人材の確保についてBCPにて予め取り決める
2025年4月30日 更新