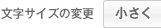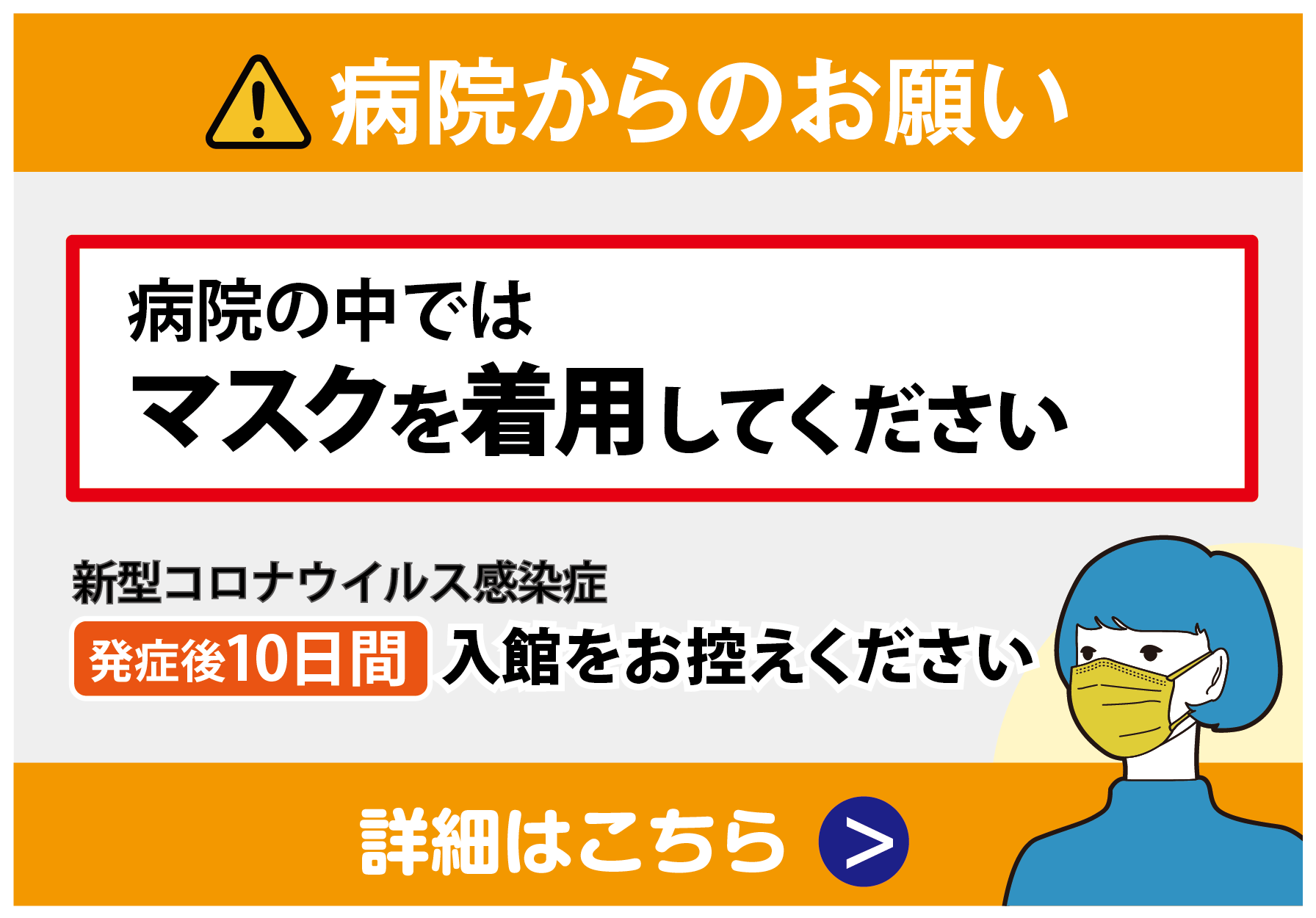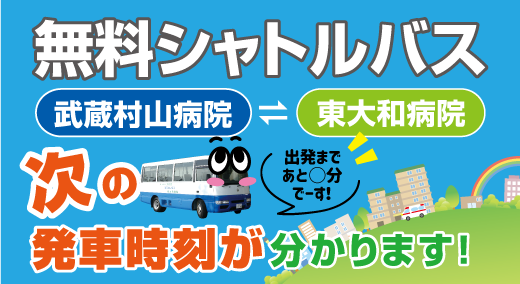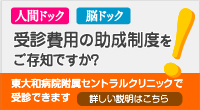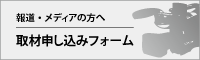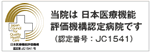医療安全管理指針
【1】医療安全に関する基本的な考え方
武蔵村山病院では、「生命の尊厳と人間愛」の理念のもと、地域の皆さまはじめ多くの患者さまに選んでいただける病院であるために、信頼される医療サービスの提供に取り組んでいきます。
私たちが接するのは「命」であるということ、そして「私たち人間はエラー(過ち)を犯すもの」という前提に、患者さまが安心して医療を受けることができ、また医療提供者が安全な医療を提供できる環境の整備とその向上に向けて取り組んでいきます。
【2】安全管理体制の整備
当院における医療事故防止及び事故発生時の対応については、院内全体が組織的に取り組むと同時に、職員一人ひとりのセルフマネージメント能力の徹底を図る事を目的に、安全管理体制を整備し機能させることとします。
医療安全管理者(専従・専任)の設置
武蔵村山病院の医療安全管理を実務的に担当するものとして専従・専任の医療安全管理者を設置しています。医療安全管理者は、病院全体にかかる安全推進活動を進めるための安全対策を企画、推進、実行、評価、フィードバックを行い、医療安全文化の醸成、再発防止案の立案、職員教育研修会の実施を行います。
医療安全管理委員会の設置
医療安全に関する院内全体の問題点を把握し、改善策や安全対策の充実、強化、評価をはじめ、組織横断的な医療安全活動の中枢的な役割を担うために医療安全管理委員会を設置しています。
医医療安全管理体制としての委員会・その他組織の設置
- リスクマネージメント委員会
- 医療機器安全管理委員会
- 医療ガス安全管理委員会
- 業務改善委員会
- 患者サービス委員会
また、関連委員会としては、
- 院内感染防止対策委員会
- 労働安全衛生委員会
その他関連組織としては、医薬品・医療機器・放射線・医療ガスの安全使用のために
- 医薬品安全管理者
- 医療機器安全管理責任者
- 放射線管理者
- 医療ガス保安監督責任者
医療安全管理室の設置
(目的・設置)
委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の安全管理を担うため、院内に医療安全管理室を設置します。
- 報告されたインシデント・アクシデントレポート[事故報告書]の受理・管理
- インシデント・アクシデントレポートの分析、予防策の検討
- システムの見直しやシステムの構築
- 各部署における安全管理に係わる指導・助言・相談
- 医療事故防止や医療安全推進等の安全管理に係わる調査活動
- 医療安全に関する職員教育などの医療安全に関する業務
(医療安全管理者)
医療安全管理者は専従と専任で活動することとし、病院全体の効果的医療安全対策を講じるためのリスクマネージメントにおいて再発防止策の立案・実行計画・実践・評価を行い、組織横断的に活動し、当病院における医療の質の確保を目指します。
- 医療安全管理者は、医療安全に関する十分な知識を有し、医療従事者の資格を有した者とする
- 医療安全管理者は、安全管理委員会の構成員とする
- 医療安全管理者は、病院長の指示を受け、各部門の医療安全推進担当者や医療安全管理部門職員と連携・協働の上業務を行う
- 病院の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど患者に対して必要な情報提供を行う
- 医療安全管理者は、以下の業務を行う
- 安全管理委員会等に参画し、安全管理に関する発言や資料の提供を行う。また、予期せぬ死亡事例など発生した場合、必要に応じて医療安全管理室長の指示のもとワーキンググループやプロジェクトチーム等、事故の内容や緊急性に応じて適宜対策を立案できる組織体制を構築する。
- 医療安全管理指針の見直しを、適宜管理委員会に提案する。
- 安全管理委員会等の活動の、定期的な評価と円滑な運営に向けて調整を行い目的に応じた活動が行えるように支援する。
- 医療安全管理者は、組織横断的な医療活動の推進や、部門を越えた連携に考慮し、職員の教育・研修の企画・実施を行う。
- 研修実施に際しては、複数回の実施やビデオ研修などにより、全員が何らかの形で受講できるようにする。
- 研修実施後は、研修担当者とともに、参加者の反応や達成度などについて研修の評価を行い、改善を行う。
- 院内巡視や事故報告による情報を基に各部署、部門における、医療安全管理指針の遵守の状況や問題点を把握し、事故発生現場や研修の場での教育に反映させる。
- 医療安全に関する情報収集を行う。
- 医療安全管理者は、医療事故及びインシデント事例報告などの、医療事故発生予防及び再発防止のための情報を収集するとともに、医療機関内における医療安全に必要情報を院内の各部署、各職員に提供する。
- 事例の分析
事故等の事例については、職員や患者の属性、事故やインシデントの種類、発生状況等の分析を行い、医療安全に必要な情報を見出す。 - 安全確保に関する対策立案
医療安全管理者は、事例の分析とともに医療安全に関する情報・知識を活用し、安全確保のための対策を立案する。 - フィードバック、評価
医療安全管理者は、医療安全に関する情報や対策等について、各部署や職員へ伝達する体制を構築する。
【3】医療に係わる安全管理のための研修
医療安全に係わる安全管理のための研修に関する基本方針
医療事故を防止するためには、医療従事者個人の資質・機能水準の向上を図ることが重要である。この向上を個人の努力にのみ依拠させるのではなく、組織全体として取り組んでいく。
医療をとりまく環境は変化していくが、それらの変化のなかにおいても、武蔵村山病院が選ばれ続ける医療機関として対応できるよう「学び続ける」ことを目的とする。そのために職種横断的、部門を越えた連携を考慮した全職員対象の研修を実施する。
医療安全管理のための研修の実施方法
- 職員研修では、事故を防止するための医療施設全体としての取り組みや個々の職員レベルでのマニュアル遵守等の取り組みを体系的に説明し、セルフリスクマネージメントの向上を目指す。院内での講義・報告会・事例分析をはじめ外部講師を招いての講習・院外講習・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読、職員参加型の研修など対象や目的に応じて教材、研修方法などを考慮して実施する。
- 新規に採用された職員に対しても体系的な安全教育を実施する。
- 上記以外の職員に対しては、新しい情報を提供することにより、安全意識の低下を防止する。
- 全職員が参加する研修は、最低1年に2回は計画的に実施する。全員が参加できるよう、研修内容の検討や同一内容の複数回実施、開催時刻や開催曜日の設定の工夫、計画的なインフォメーションによる周知徹底などを図る。また、不参加者へのフォローアップ研修も実施する。
- 全員参加研修のほかにも、職種別、部門別に各分野のより専門的な院内研修の企画、院外研修への参加を行い、現場に反映させる。
- 院内で勤務する外部委託職員も積極的に参加できるようにする。
- 研修の評価を行い、改善を図る。
【4】事故報告などの医療に係わる安全の確保を目的とした改善方策に関する基本方針
医療安全管理マニュアル
医療安全管理マニュアルを整備し、職員が「行うべき」「行ってはならないこと」の徹底を図る。マニュアルは、医療安全管理室内にファイリングの他、院内LANにより、職員がいつでも確認できるように整備する。
医療事故報告制度
インシデントまたはアクシデントが発生した場合の報告制度の徹底を図り、事故防止、再発防止に活用する。
職員教育の充実
医療安全管理に関する知識、技術の維持、向上、徹底を図るための職員教育の充実に努める。
業務管理および業務改善
- 業務基準、業務手順の整備業務基準、業務手順の整備
- 職種、部門ごとの専門性の向上
- 医療事故報告例等の情報の活用
- 個人情報の保護への配慮
- インフォームド・コンセントの徹底
- 患者さまやご家族などからの病院に対するご意見
報告基準
- 医療安全管理指針(Ⅴ-2)に準じる
【5】医療事故発生時の対応に関する基本方針
救急措置の最優先
医療提供側過失によるか否かを問わず、患者さまに望ましくない事象が生じた場合には可能な限り、当院内の総力を結集して患者さまの救命と被害の拡大防止に全力を尽くします。(予期せぬ死亡時対応マニュアルに準ずる)
また、当院のみで対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材の提供を求めていきます。
報告
- 前項の目的を達成するため、事故の状況・患者さまの現在情報などを、定められた報告手順に従って上司に報告し、定められた書式のインシデント・アクシデントレポートを提出する。ただし、緊急の場合は、直ちに口頭で報告する。
- 病院長は、必要に応じて関連機関への協力要請を依頼する。
- 夜間、休日などで主治医が不在の場合は、当直医師に連絡をする。当直医師は事故の重大性を考慮し、病院長に報告する。
患者さま・ご家族への対応
- 事故発生時、救命処置の遂行に支障をきたさない限り、可及的速やかに事故の状況・現在実施している回復措置、その見通し等について、患者さま本人・ご家族等にできるだけ速く、誠意をもって説明する。
- 患者さま・ご家族への事故の説明等は複数で臨み、一人では行わない。原則当該部門長、病院幹部が説明者となり、客観的な事実の説明を行うとともに、病院側の過誤が重大で明白な場合は責任者が率直に謝罪する。事故発生の報告を受けた当該部署部門長等は、患者さま側への説明方法を決定する。
- 事故発生翌日以降の対応としては、病院は事実の調査や原因の検討を行うとともに、患者さま・ご家族等の心に与える影響を最大限に配慮し、隠し立てのない事実の説明と率直な謝罪、再発防止への取り組みなどを説明して誠実に対応する。
経過の記録
- 事故発生からの対応、経過についてはその報告、対応を行った職員が、その事実について経時的、客観的かつ正確に記録する。
- 説明を行った職員は、その事実及び説明の内容及び同席者並びに説明を受けた相手側の名前・患者さまとの続柄・患者さま側からの質問等を診療録・看護記録等、自らが患者さまの医療に関して作成すべき記録をする。
- 死亡診断書の作成は、責任者と複数で行い、慎重かつ緻密に対応する。
Ai(死亡時画像診断)・病理解剖について
異状死としての届出が必要な場合で、かつ死亡原因の特定のためにAi・病理解剖の必要性がある場合は、その必要性について説明し承諾を求める。承諾が得られなかった場合については、その旨を必ずカルテに記録する。
監督官庁への届出
- 医療過誤によって死亡または、傷害が発生した場合もしくは、その疑いがある場合には、報告を受けた病院長は、患者さま・ご家族等に説明した後、所轄警察署に届出を行う。
- 異状死が発生した場合の警察への届出は、医師法21条により24時間以内に行う。
- その他、医療法第21条の規定により、医師は、死体または妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認められた場合、24時間以内に所轄警察署に届け出ることが義務付けられている。
- 医警察への届出を行うにあたっては、原則として患者さま・ご家族に前もって説明を行い、承諾を得る。
事故の分析、評価と事故防止への反映
事故の原因分析と評価検討を加え事故の再発防止に反映させる。
公表
- 事故の公表にあたっては、病院長は緊急に医療安全管理委員会を招集し審議し、必要に応じ、顧問弁護士や関係部署で協議を行い、事前に患者さま・ご家族と話し合いを行った上で病院長の判断のもとに病院長が行う。
- 公表に関しては、範囲と手段を明確に決め、患者さまのプライバシーの保護には最大限の配慮をする。
- 事前に患者さま・ご家族に十分に内容を説明し、同意を得る事を原則とする。
院内医療事故調査委員会の設置
届出や公表する事例、届出公表判定会議や過失判定会議・対応検討会議で必要と決定した事例については、病院長の判断で院内医療事故調査委員会を事例毎に設置して原因究明と再発防止策の検討を行う。調査結果は口頭や書面により患者家族が希望する方法で説明するよう努める。
医療事故調査・支援センターへの届出事例は、調査結果を医療事故調査・支援センターへ報告すると共に、医療事故調査・支援センターによる調査を別途依頼する。
事故を起こした職員への対応
- むやみに個人の責任のみを追及することなく、組織としての問題点を検討する。
- 直接の上司が中心となり、事故を起した職員への精神的ケアを行う。必要に応じ、産業医への相談、精神科医への相談ができるように配慮する。
- 職員同人のプライバシーの保護にも配慮する。
【6】医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針
医療安全管理指針については、院内電子カルテに搭載し、職員が容易に閲覧できるようにする。
また、患者さま及びご家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応ずる。武蔵村山病院ホームページ上でも閲覧可能とする。
【7】患者からの相談に関する基本方針
病状や治療方針などに関する患者さまからの相談に対しては誠実に対応する。
また、必要に応じて、多職種によるカンファレンスを開催する。
【8】その他
- 職員の責務
職員は職務の遂行にあたっては、常日頃から医療事故の発生を防止するための細心の注意を払わなければならない。 - 医療事故報告書は医療安全管理室を経て総務課にて保管する。
- 本指針は、医療安全管理委員会において定期的に(1年1回以上)、見直しを議事として取り上げ、検討することとする。
- 本規定の改訂は、医療安全管理委員会の決定により行う。
2025年4月