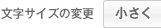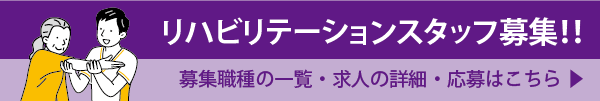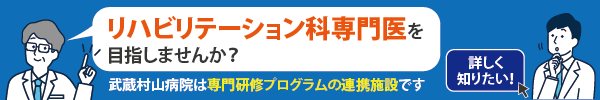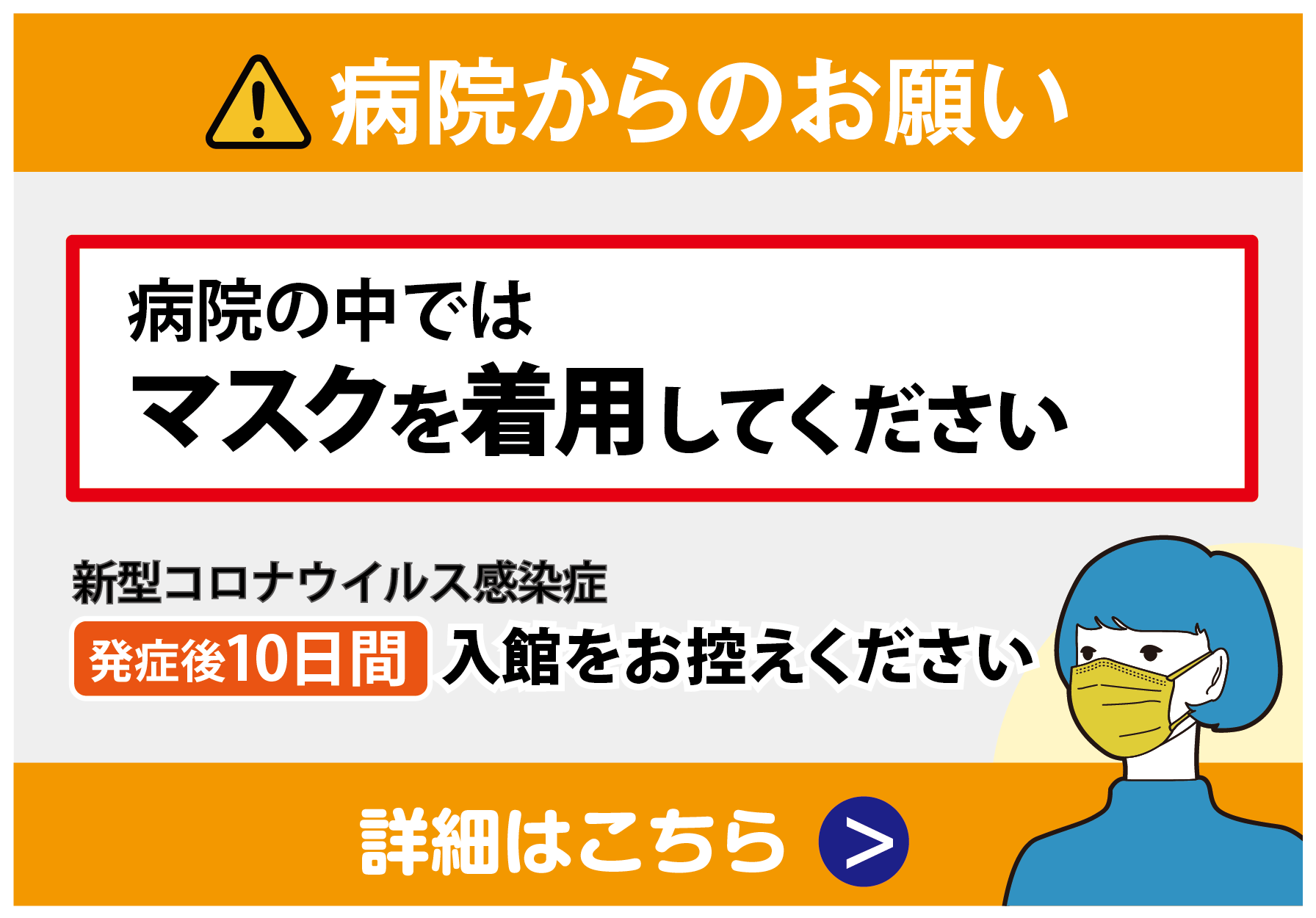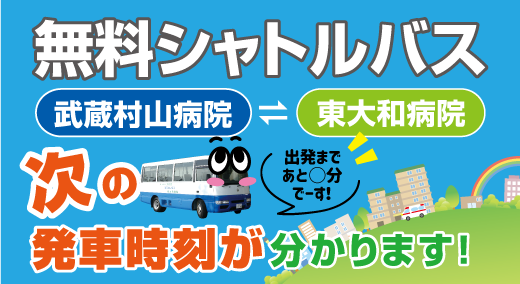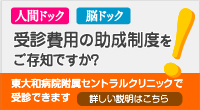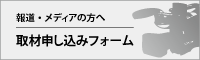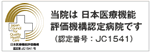リハビリテーションセンターにおけるチーム医療
 リハビリテーション診療を運営していく上で、職員が働きやすく、質の高いチーム医療が展開されることが職員のモチベーション維持に必要と考えています。これがチームとして患者さまへの良質なリハビリテーション診療の提供に繋がり、一日も早く納得できる住み慣れた日常生活に送りだせると思います。
リハビリテーション診療を運営していく上で、職員が働きやすく、質の高いチーム医療が展開されることが職員のモチベーション維持に必要と考えています。これがチームとして患者さまへの良質なリハビリテーション診療の提供に繋がり、一日も早く納得できる住み慣れた日常生活に送りだせると思います。
リハビリテーションセンターでは、他診療科の協力も得ながら、多職種によるチーム医療の能率よい運営を目指しています。2013年度より、歯科医師と歯科衛生士との摂食嚥下チーム、管理栄養士とのリハビリテーションNST、皮膚科医とWOCナースの回診チームなどと協働。その後、泌尿器科医師との排泄ケア回診、神経内科医と精神科医との認知症対策チームによるBPSD回診を開始。更に2018年4月からはセラピスト・看護師・介護福祉士の3職種の早出・遅出勤務による病棟でのADL自立支援を開始し、セラピストが患者さまの朝晩の様子を把握できるようになりました。
右図に示されるように、沢山の職種がチームとなり、患者さま各々に最適な治療計画を立てて共有・協働し、リハビリテーション治療に当たり、医療・介護サービスを提供します。
2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう「地域包括ケアシステム」が策定されました。これに従って退院後の患者さまの生活を、本人のご希望に沿った形で家庭や社会へ参加・復帰できるように、情報提供や各種手続きなどのサポートをします。
チーム医療に携わるスタッフ
ここに各職種の業務内容が表示されます。
医師
回復期リハビリテーション(以降リハビリ)病棟52床を中心に、外来と急性期リハビリも併せて診療を行っています。当科の診療理念は、患者さまの在宅復帰を前提とした「医師主導による短期集中リハビリ治療」を提供し、出来るだけ早く、身体機能向上と最大能力の獲得を図ります。医師の責任としてこの理念を以て関係する各職種とともにリハビリ診療を実施し、退院後のスムーズな社会参加が可能となるように努めています。
理学療法士
病気やけがによって動作能力が低下した患者さまを対象に、運動療法や温熱など物理的な手段を用いてリハビリを行います。「起き上がる/立ち上がる/移動する」など、生活を送る上で基本となる動作の改善を目指すほか、福祉用具の選定や使用など身体状況に合わせた社会生活への調整も行います。
作業療法士
病気やけが等によって心身機能に障害がある患者さまを対象に、生活に関わる活動や手芸、余暇などの作業活動や、運動を通じた機能の回復、生活の再建を図っています。トイレや着替え、家事といった生活全般のリハビリや運動機器を用いた手のリハビリのほか、認知機能に関わるリハビリも行い、安全に日常生活を送れるよう支援しています。また、職場復帰などの社会参加に向け必要な評価・リハビリを実施しています。
言語聴覚士
言葉をうまく話せない「失語症」、発音がスムースにできない「構音障害」、その他「高次脳機能障害」などコミュニケーション障害の患者さまを対象にリハビリを行います。状態や対応方法をチームで共有し、ストレス無く入院できるよう関わります。また、飲食物がうまく飲み込めなくなる「嚥下障害」に対しても、状態に合わせた食事や食べ方など提案し、安全に食事できるようチームでサポートします。
ご家族にも情報共有し、退院後も安全にその人らしく生活できるようフォローします。
公認心理師
患者さまが安心して入院生活を過ごし、家庭復帰や社会復帰ができるよう、医師の指示に基づいて患者さまとご家族の心理的サポートを行います。高次脳機能障害や認知症などの症状が疑われる方に対しては、神経心理学的検査を通して、症状の有無や程度を確認させていただきます。病気や怪我の後に生じるお困りごとが少しでも減らせるよう、患者さま一人ひとりに合わせた対応方法をご提案いたします。
看護師
医師の診察補助の他、リハビリがスムーズに行えるように全身状態・栄養状態を整えるとともに、療養上のサポートや精神面のケアを担っています。また、病棟生活すべてがリハビリであると考え、リハビリ訓練で獲得した「できるADL/動作」を日常生活における「しているADL/動作」に繋げられるよう、リハビリテーション看護を行っています。
介護福祉士
日々リハビリされている患者さまに対し、日ごろの入院生活全般(食事・入浴・排泄)を介助していきます。そのなかで各職種と連携をとり、情報を提供(共有?)し、向上性のある回復期リハビリテーション病棟を目指しています。また、退院前の患者さまのご家族へオムツ交換等の指導や、患者さま本人に合った現実的なライフスタイルの提案にも携わっていきます。
歯科医師
「咬むこと(咀嚼)」から「飲み込むこと(嚥下)」にかけてお困りの患者さまに対してサポートを行います。特に「良く咬んで食べること」が大切と心がけてリハビリを行っています。また、全身疾患や服薬、ADL低下があると抜歯を含めた歯科受診が難しくなるため、高齢者歯科の専門医が整った診療環境で処置します。う蝕や歯周病をきちんと治療して、美味しく食べることができる清潔な口腔へと導きます。
歯科衛生士
口腔機能は摂食嚥下のプロセスの役割を担っていることはもとより、呼吸・会話など人としての重要な機能を担う器官でもあります。何らかの障害を持った患者さまに対し、口腔の専門職である歯科医師・歯科衛生士が早期から関わるのは当然の役割と考えています。口腔ケア・口腔リハビリなど、口腔機能が最大限生かせるよう口腔の維持・向上に関わるあらゆるサポートを行います。
管理栄養士
患者さまが元気になるためのリハビリには十分な栄養が必要です。一人ひとりの病状や体格、活動量に合わせた食事提供のほか、直接患者さまのもとへ伺って食事摂取状況の確認や要望等の聞き取りを行うことで、リハビリで最大限の力が発揮できるよう食事からサポートしています。また、週1回の栄養カンファレンスでは医師・看護師・リハビリスタッフ・管理栄養士でリハビリ状況等の評価を行い、退院に向けて多職種で連携を取っています。
薬剤師
患者さまの「どのように生活していきたいか」の想いに寄り添いながら、患者さまのご意向の実現のために医師・看護師・リハビリスタッフ等の医療チームやご家族との連絡調整を行ったり、必要なサービス・制度を円滑にご利用いただけるよう橋渡しを行いながら、在宅含めた社会復帰のお手伝いをしています。
医療相談員
薬の飲み合わせ確認等の通常業務に加え、患者さま一人ひとりに合わせた医療が提供できるよう、看護師・理学療法士・作業療法士との多職種カンファレンスを入院時に行っています。また、一般病棟と比較して長期入院になることが多いため、日々の患者さまの状態に合わせて医師・看護師等と相談し、薬剤の調整の提案や、在宅復帰後も服薬を継続していただけるよう服薬カレンダーを利用した服薬指導を行っています。